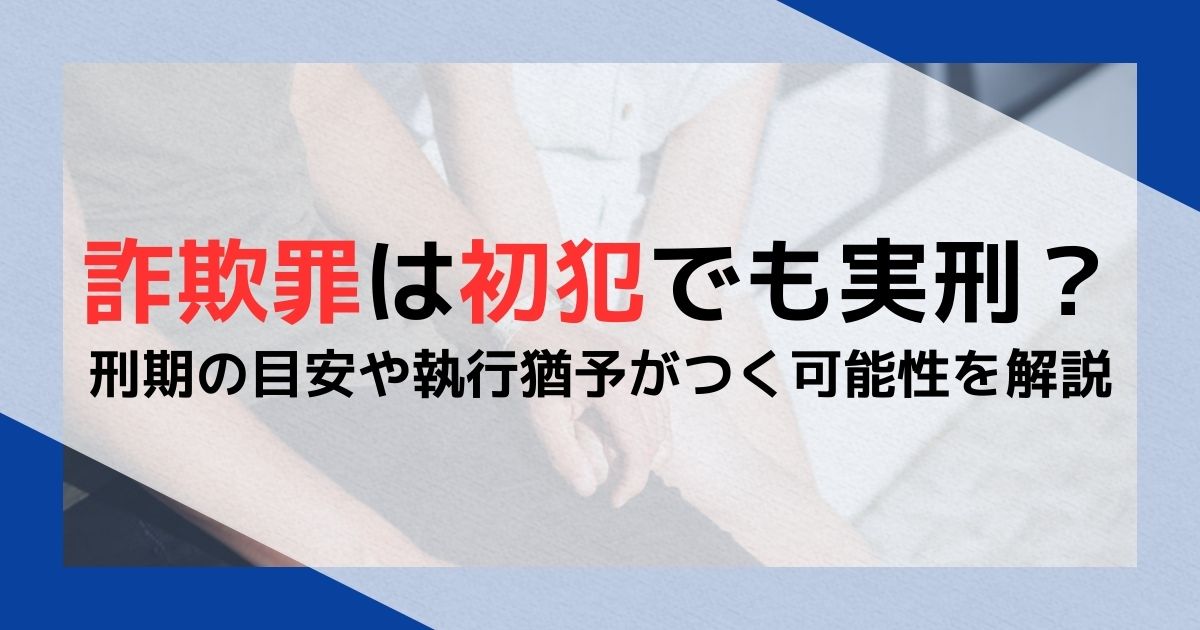詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、有罪になると必ず懲役刑に科されます。
詐欺罪では、初犯であっても実刑判決となり刑務所に入らなければならなくなるケースもあります。
ただし、執行猶予付き判決を獲得して実刑を回避できれば、これまでと変わらない日々を自宅で過ごすことが可能です。
「初犯で執行猶予が付く可能性はどの程度あるのか」
「初犯の場合どのような詐欺事件が実刑になりやすいのか」
と、さまざまな疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
実際にグラディアトル法律事務所が扱った詐欺罪での初犯の事件のなかにも、罪が重くなりやすい特殊詐欺の受け子・出し子で逮捕された20代男性を弁護し、実刑を避けて執行猶予を獲得したものがあります。
そこで本記事では、詐欺罪の初犯に対する刑罰について詳しく解説します。
不起訴処分・執行猶予を獲得するためのポイントなどもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
詐欺罪は初犯でも懲役の実刑になることがある
詐欺罪で検挙された場合、初犯であっても懲役の実刑になることがあります。ここでは、詐欺罪が比較的実刑になりやすい犯罪といえる2つの理由を詳しく見ていきましょう。
そもそも詐欺罪は起訴される可能性が高い
そもそも詐欺罪は起訴される可能性が高い犯罪のひとつです。
令和5年版犯罪白書によると、令和4年において詐欺罪で起訴されたのは7,669件、不起訴となったのは8,324件とされており、起訴率は約48%に及びます。
犯罪全体の起訴率が約32%にとどまることを踏まえると、明らかに高い水準にあるといえるでしょう。
初犯であることは、起訴・不起訴の判断において有利な事情として扱われますが、それでも詐欺罪で起訴される可能性は十分残されています。
そして、日本の裁判における起訴後の有罪率は99%以上です。
詐欺罪で起訴された場合には、ほぼ確実に有罪となり、懲役刑が科せられてしまいます。
有罪判決が下された事件のうち執行猶予がつくのは6割程度
裁判で有罪となり、懲役刑が言い渡されたとしても、執行猶予がつけば実刑を回避できます。
しかし、詐欺罪で執行猶予付き判決を勝ち取ることは簡単ではありません。
令和4年においては、詐欺罪で懲役刑となった3,239件のうち、全部執行猶予となったのは1,927件と約6割にとどまります。(参考:令和5年版犯罪白書|法務省)
また、執行猶予がつく可能性があるのは「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金刑」となった場合のみです。
詐欺罪では3年を超える懲役刑になるケースも多く、その場合には、そもそも執行猶予の対象になり得ません。
関連コラム:
振り込め詐欺は初犯でも実刑?執行猶予を獲得するための対処法を解説
詐欺罪の初犯でも懲役の実刑になりやすいケース
次に、詐欺罪の初犯でも懲役の実刑になりやすい5つのケースについて解説します。
犯行が悪質で重大な結果が生じている場合
初犯であっても、犯行が悪質で重大な結果を引き起こした場合は、懲役の実刑判決を受ける可能性が高くなります。
たとえば、組織的な犯罪で多額の金銭を騙し取った場合は、被害者本人や社会に与える影響が大きく、加害者が負うべき責任も重くなるため、裁判官の判決は当然厳しいものになるでしょう。
実際に、振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺の事案では、たとえ末端の受け子や出し子であっても、初犯で実刑判決を受けるケースは数多く見受けられます。
被害者の処罰感情が大きい場合
被害者の処罰感情が強い場合も、懲役の実刑判決を受ける可能性が高くなります。
裁判官は量刑を決定する際、被害者の心情を重要な要素として考慮するためです。
一方で、被害者自身が「厳しい処罰は望まない」などと意思表示している場合は、量刑が軽くなることもあります。
そのため、加害者は真摯に反省し、被害弁償に努めるなど、被害者感情の緩和に努めることが重要です。
反省の態度がみえない場合
初犯であっても、加害者に反省の態度が見られない場合は、懲役の実刑判決が下されることがあります。
裁判官は、反省の有無・程度をもとに、加害者の再犯リスクや更生の可能性を判断するためです。
また、社会的制裁の必要性や被害者感情の観点からも、反省のない加害者に対しては厳しい判断が下される傾向があります。
加害者が反省の態度を示すためには、反省文・謝罪文を書く、再発防止策を提示するなどの方法をとるのが効果的です。
口頭で反省の態度を示すだけではあまり意味がなく、具体的な行動を伴うことがポイントといえます。
被害弁償がおこなわれていない場合
被害弁償がおこなわれていない場合も、懲役の実刑判決になりやすいケースのひとつです。
詐欺の被害者は精神的苦痛に加えて、経済的苦痛を抱えることになるため、損害の回復は最優先されるべきものといえます。
そのなかで、被害弁償をおこなっていないのであれば、反省の程度が不十分だと判断されてしまうのです。
被害金をすでに使っている場合など弁償が難しい状況でも、家族や知人からお金をかき集めたり、返済計画を示したりと弁償の意思・努力を示すことが、実刑回避につながります。
複数の余罪がある場合
詐欺罪の初犯であっても、複数の余罪がある場合は懲役の実刑判決を受ける可能性が高くなります。
余罪の存在は犯罪傾向や常習性を示すため、余罪自体は起訴されなかったとしても、本罪の量刑に影響を与える可能性があるのです。
また、余罪も含めて起訴されると「併合罪」として扱われ、刑の上限・下限が加重される点にも注意が必要です。
発覚していない余罪がある場合は、まず弁護士に相談し、どのように取り扱っていくべきか慎重に判断するようにしましょう。
詐欺罪の刑期は何年?初犯の量刑相場
詐欺罪で懲役刑が科せられた場合、刑期は1〜3年程度が平均といえます。
令和5年版犯罪白書によると、令和4年に有期懲役となった3,239件のうち、最も割合が多かった刑期は「2年以上3年以下」で1,705件、次に「1年以上2年未満」で1,063件でした。
(参考:令和5年度犯罪白書|法務省)
初犯であれば、裁判官が量刑を判断する際に有利な事情として扱われるため、刑期も短くなりやすいといえます。
しかし、懲役の刑期は被害の大きさや被害弁償の有無などを総合的に考慮したうえで、判断されるものです。
たとえ初犯であっても、重大な詐欺事件に関与した場合などは、3年を超える刑期を言い渡され、執行猶予がつかない可能性も十分考えられます。
関連コラム:
詐欺罪の量刑相場は懲役1~3年!量刑判断では被害金額が重要な要素
詐欺罪の初犯を取り扱った判例
ここでは、詐欺罪の初犯を取り扱った判例を2つ紹介します。
複数人に対する投資詐欺で4,000万円以上を騙し取った事例|懲役5年
FX取引の運用名目で、4名の被害者から4,000万円以上の大金を騙し取った組織的詐欺の事例です。
詐欺の一端を担った日本人が裁判にかけられました。
【事案概要】
①加害者は中国人を含む多数の人物と詐欺を計画した ②FXの情報交換を装うLINEグループに被害者らを参加させ、自作自演により信用を得た ③指定口座に入金すれば、FX取引で運用されるものと誤信させ、4名から合計4,030万円を騙し取った |
(佐賀地判令和6年7月25日)
本事案において、加害者には前科もなく、双極性障害の持病を抱えるなど考慮されるべき事情が複数ありました。
しかし、中国人ら上位者の指示に従い、日本語でのやり取りや詐欺で用いる動画の制作など、詐欺行為に不可欠な役割を果たした罪は重く、実刑は免れないものと判断され、執行猶予なしの懲役5年が言い渡されました。
ワクチン接種業務の委託料約7万円を自治体から騙し取った事例|懲役2年・執行猶予3年
クリニックの院長がワクチン接種業務の委託料を自治体から騙し取った事例です。
【事案概要】
①医師は全国知事会等から委託を受け、新型コロナウイルスの予防接種事業に参加した ②不正な行為と知りながら、自身が主催するセミナーでワクチンを接種しなくても接種済証を発行する旨の資料を配布した ③セミナーの参加者などの依頼に応じ、虚偽の内容が記された15名分の予診票などを5つの地方公共団体に送付し、委託料合計6万8,310円を詐取した |
(東京地判令和5年5月12日判決)
裁判において、医師がおこなった一連の行為は特別な権限を濫用した悪質なものだと批判されました。
一方で、被害金を全額弁償しており、前科もなく反省の意思もみられることから、懲役2年・執行猶予3年の判決が言い渡されています。
詐欺罪の初犯で不起訴処分・執行猶予を獲得するためにできること
次に、詐欺罪の初犯で不起訴処分・執行猶予を獲得するためにできることを解説します。
被害者との示談を成立させる
不起訴処分や執行猶予の獲得を目指すのであれば、被害者との示談成立を最優先に考えましょう。
示談は当事者間で和解が成立していることの証明になるため、検察官が「あえて厳しい刑罰を与える必要はない」と判断する可能性が高くなります。
また、示談の成立によって反省の態度や更生の意思を示せば、起訴・不起訴や量刑の判断において有利な事情として扱われるはずです。
ただし、当事者間で直接示談交渉することはおすすめしません。
そもそも怒りや恐怖の感情を抱いた被害者が示談に応じてくれる保証はなく、交渉できたとしても、高額な示談金を要求されるおそれがあります。
そのため、示談に関することは法律の専門家であり、交渉のプロでもある弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。
関連コラム:
更生に向けた環境を整える
更生に向けた環境を整えることも、不起訴処分や執行猶予を獲得するために欠かせないポイントのひとつといえます。
検察は起訴・不起訴や量刑を判断する際に、再犯リスクや社会復帰の可能性を重視するためです。
たとえば、詐欺に手を出した原因がギャンブルや浪費にあるのであれば、医療機関で依存症の治療を受けてみるのもよいでしょう。
また、人間関係を見直す、実家に戻り親の目が届く範囲で生活するなどの方法も挙げられます。
自身の行動や思考を客観的に分析し、更生に向けた環境整備の方法を適切に選択・実行するようにしましょう。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
詐欺罪の初犯で不起訴処分や執行猶予を獲得するためには、刑事事件に精通した弁護士に相談することも大切です。
経験豊富な弁護士であれば、個々のケースに合わせて、今やるべきことを適切に判断してくれます。
具体的には、以下のようなサポートが期待できるでしょう。
- ・逮捕直後の迅速な接見
- ・接見禁止の一部解除申請
- ・自首の同行
- ・取り調べでの振る舞い方についてのアドバイス
- ・早期釈放に向けた弁護活動
- ・被害者との示談交渉
- ・再犯防止策の検討
- ・捜査機関に対する働きかけ
- ・公判手続きの準備と対応
実際にグラディアトル法律事務所では、振り込め詐欺の受け子・出し子で逮捕された20代男性を弁護し、解決へと導いた実績があります。
男性は罪が重くなりやすい特殊詐欺に加担していたため、初犯ではあったものの、実刑になる可能性が残されていました。
そこで、まずは弊所弁護士が早急に被害金を弁済し、示談を成立させました。
そのうえで、男性の反省と更生への強い意志を意見書にまとめ裁判所に提出し、家族にも情状証人として証言してもらうよう働きかけた結果、執行猶予付き判決が言い渡されたのです。
このように弁護士が早期に介入できれば、実刑を回避できる可能性が大きく高まることを覚えておきましょう。
関連コラム:
振り込め詐欺の初犯!受け子と出し子で逮捕されるも執行猶予となった事例
【加害者向け】詐欺事件を今すぐ弁護士に相談するべき3つの理由!
詐欺罪の初犯に関してよくある質問
最後に、詐欺の初犯に関してよくある質問を紹介します。
同様の疑問を抱えている方は参考にしてみてください。
初犯であれば逮捕の可能性も低くなる?
詐欺罪に関しては、初犯だからといって逮捕の可能性が大きく下がるわけではありません。
令和5年版犯罪白書によると詐欺罪の逮捕率は約48%と高く、初犯であっても逮捕される可能性は十分に残されています。
また、詐欺罪は逮捕後の勾留請求率も99%を超えており、一度逮捕されると長期間の身柄拘束を覚悟しなければなりません。
詐欺未遂の初犯でも実刑になることはある?
詐欺未遂の初犯であっても、実刑になることはあります。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」です。
未遂かつ初犯であれば、通常の詐欺罪より量刑が軽くなる傾向にありますが、必ずしも実刑を回避できるわけではありません。
特殊詐欺のような重大な詐欺事件に関与していた場合や、反省の態度がみえない場合などは、実刑判決が下される可能性もあります。
そのため、未遂の初犯だからといって安心せず、弁護士と相談しながら適切な対応をとり、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すことが重要です。
関連コラム:
詐欺未遂罪とは?成立要件や刑罰・量刑、処分を軽くするための対処法
未成年が初犯で詐欺事件を起こした場合はどうなる?
未成年が初犯で詐欺事件を起こした場合、少年審判の対象となるケースが一般的です。
少年審判では、未成年の健全な育成と再犯防止のために、刑罰ではなく保護処分が決定されます。
保護処分には保護観察や少年院送致などがあり、事案の重大性や少年の反省の程度によって判断されることになるでしょう。
なお、犯行が特に悪質な場合や被害が大きい場合は検察官送致となり、成人と同様に刑事裁判を受ける可能性もあります。
詐欺事件を起こしたときはグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ・詐欺罪は初犯でも懲役の実刑になることがある
- ・犯行が悪質で重大な結果が生じている場合や被害者の処罰感情が強い場合、被害弁償がおこなわれていない場合などは、初犯でも実刑になりやすい
- ・詐欺罪で懲役刑が科せられた場合、刑期は1〜3年程度が平均
- ・起訴処分・執行猶予を獲得するためには示談成立や、更生に向けた環境構築が重要
詐欺罪の初犯であれば、起訴・不起訴や量刑の判断において有利に働くことは確かです。
しかし、犯行の態様によっては、初犯であっても実刑判決になる可能性は十分残されているため、できるだけ早く弁護士に相談・依頼し、サポートを求めるようにしましょう。
グラディアトル法律事務所は、多岐にわたる法律分野のなかでも、刑事事件に注力している点を強みのひとつとしています。
これまでにも数多くの詐欺事件を取り扱い、解決へと導いてきました。
弊所は初回相談無料で、LINE相談にも対応しています。
経験豊富な弁護士が24時間体制で相談に応じているので、少しでも不安や悩みがある方は、いつでもお気軽にお問い合わせください。