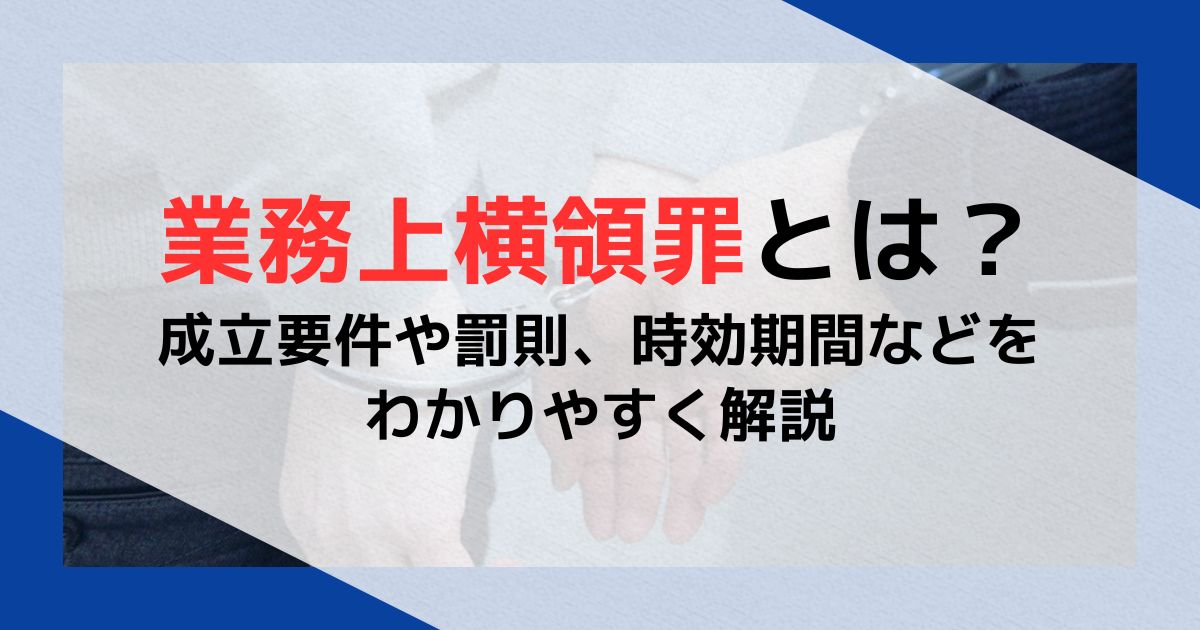業務上管理している金品などを私的利用した場合は、業務上横領罪の罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪は重い刑罰が定められているため、加害者になったときは、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて迅速に対策を講じていかなければなりません。
しかし、自身が犯した犯罪についての基本的な知識がなければ、今後の対応を適切に検討することも難しいでしょう。
そこで本記事では、業務上横領罪の成立要件・罰則・時効期間などを解説します。
実際の判例も紹介しながら、加害者側が知っておくべきポイントをわかりやすくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
業務上横領罪とは?
まずは、業務上横領罪とはどのような犯罪なのかを深掘りして解説します。
業務上横領罪の成立要件
業務上横領罪は「業務上自己が占有する他人の物を、不法に自分のものにした」場合に成立する犯罪です。
具体的な成立要件としては、以下の4点が挙げられます。
「業務性がある」は、事務作業に反復・継続して取り組んでいる状態のことです。
会社の仕事だけではなく、自治会やボランティア団体などでの活動にも業務性は認められます。
「委託信任関係に基づいて対象物を占有している」は、当事者間の信頼関係を前提に、物を預かったり、管理したりしている状態のことです。
「対象物が他人の所有物である」「横領している」は、他人の物を自分の物のように使用したり、売却したりする行為を指すものと考えてください。
たとえば、経理担当者が会社名義口座から自己名義口座へ送金したり、会社備品を無断で転売したりすると業務上横領罪が成立します。
混同されやすい犯罪との違い
業務上横領罪は、ほかの犯罪との区別がつきにくい部分もあるので、混同しないように注意しておく必要があります。
ここでは、業務上横領罪と単純横領罪・窃盗罪・背任罪の違いを詳しくみていきましょう。
単純横領罪との違い
業務上横領罪と単純横領罪は、他人の物を不法に自分のものにする犯罪である点は共通しています。
そのなかで、両者が大きく異なるのは「業務性」の有無です。
業務上横領罪は、職務に関連して財産管理を委託されている場合に適用されます。
たとえば、経理担当者が会社の金庫にある現金を着服した場合は、業務上横領罪が成立します。
一方、単純横領罪は、業務と無関係の横領に対して適用される犯罪です。
友人から預かった物を無断で売却したり、レンタルで借りたもの返却せずに使い続けていたりすると、単純横領罪の罪に問われます
なお、刑罰の違いは以下のとおりです。
- ・業務上横領罪:10年以下の懲役
- ・単純横領罪:5年以下の懲役
業務上横領罪は会社の信用を裏切る重大な犯罪であり、被害額も大きくなりやすいため、単純横領罪より重い刑罰が規定されています。
【窃盗罪との違い】
業務上横領罪と窃盗罪は、他人の財物を不法に自己のものとする点で共通していますが、加害者の立場・占有権原に大きな違いがあります。
まず、業務上横領罪は業務上の委託信任関係を前提とした犯罪です。
占有権原が認められたものを横領した場合に、業務上横領罪が成立します。
たとえば、会社の現金管理を任されている従業員が金庫の現金を私的利用した場合は、業務上横領罪の罪に問われる可能性が高いでしょう。
一方、窃盗罪はそもそも占有権原をもたない人物が他人の財物を盗んだ場合に成立する犯罪です。
たとえば、アルバイト店員が管理を任されていない金庫から現金を持ち出す行為は窃盗罪にあたります。
なお、窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
【背任罪との違い】
背任罪と業務上横領罪は、いずれも他人からの信頼を裏切る犯罪ですが、財物の移転があるかどうかに違いがあります。
業務上横領罪は、財物の移転をともなう犯罪です。
一方、背任罪は、任務に背いて財産上の損害を与える行為を指し、必ずしも財物の移転がともなうわけではありません。
たとえば、会社の企業秘密を漏らして売り上げが下がった場合、加害者は財物を得ていないので業務上横領罪には該当しませんが、結果的に損害を与えているので背任罪が成立するものと考えられます。
また、業務上横領は特定の目的がなくても成立しますが、背任罪は自分・第三者の利益を図る目的や、背任の相手に損害を与える目的があった場合に成立する点も大きな違いといえるでしょう。
なお、背任罪の刑罰は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
業務上横領罪の罰則に罰金はない!有罪になると「10年以下の懲役」に処される
業務上横領罪の罰則は「10年以下の懲役」です。
罰金刑は設けられていないので、裁判で有罪になると必ず懲役刑が科せられます。
厳しい罰則が設けられている理由は、業務上横領が会社との信頼関係を裏切る重大な犯罪だからです。
また、会社から管理を任される財産は高額になるケースが多く、横領による損害が大きくなりやすいことも、刑罰が重く設定されている理由のひとつといえます。
なお、業務上横領では、刑事罰のほかに民事上の損害賠償責任を負う可能性が高い点にも注意が必要です。
業務上横領罪の量刑に影響する要素
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、実際の量刑は以下のような要素を総合的に考慮して決定されます。
業務上横領罪の量刑判断において重要視されるのは、被害金額です。
金額が大きいほど刑が重くなる傾向にあります。
ケースバイケースですが、被害金が100万円を超えると執行猶予がつかず、実刑になる可能性が高まるものと考えておきましょう。
そのほか、巧妙な手口を用いていた場合や、遊興目的など身勝手な動機があった場合なども悪質な犯行とみなされ、量刑が重くなりやすいです。
一方で、被害弁償によって示談が成立しており、加害者本人も深く反省している状況であれば、執行猶予がついたり、刑期が短くなったりすることもあります。
関連コラム:業務上横領の量刑はどのくらい?執行猶予や刑期に影響する要因も解説
業務上横領罪の判例
ここでは、業務上横領罪の判例を3つ紹介します。
司法書士が顧客の口座から自己名義口座に750万円を振り込んだ
遺言執行者に選任された司法書士が、顧客から預かっていた相続財産のうち750万円を自己名義口座に移し、私的に使用した事案です。
【事案概要】
| ①司法書士のAは遺言執行者に指定され、被相続人Bの財産を管理していた ②AはB名義の口座から約750万円を払戻し、自己名義口座に入金した ③A名義の口座残高は個人的な用途での費消により減少していた ④AはBの相続人と相続財産の扱いに関してトラブルになった ⑤司法書士会の調査を受ける過程で、Aは横領した額を補填し、自己名義口座から事務所の預り金口座に出金した |
(神戸地判平成26年9月2日判決)
本事案において、Aの横領は司法書士に対する社会の信用を失墜させる行為であり、厳しく非難されるべきものと判断されました。
一方で、公私混同による一時的な私的流用の範囲にとどまることや、被害者と和解が成立していること、司法書士登録を取消されていることなどが考慮され、懲役2年6月・執行猶予3年の判決が下されました。
カンツリークラブの代表取締役が業務上預かっていた計1億3,500万円を横領した
カンツリークラブなどを経営する会社の代表取締役が業務上預かっていたお金の横領を繰り返し、被害金が計1億3,500万円にまで達した事例です。
【事案概要】
| ①Aは自社で経営するカンツリークラブの施設改善をおこなうことにした ②施設改善の資金を捻出するため、業務上預かっていた現金を横領し、信用取引を始めた ③信用取引はうまくいかず、損失を回復するために横領を繰り返し、横領額は計1億3,500万円に及んだ |
(岡山地判平15年1月29日判決)
本事案は大きく報道され、会社の信用を傷つけるなど重大な結果を招きました。
また、裁判においても、代表取締役としての権限を利用した常習的かつ悪質な犯行であり、
取引業者に領収証を偽装させるなど巧妙な手口を用いた点が指摘されました。
一方、4,000万円程度の被害弁償がおこなわれていることや、そもそもの発端は会社のためであり、私利私欲のための使い込みではなかった点は情状酌量の余地ありと判断されました。
また、多くの人がAの仕事ぶりや人柄を高く評価し、寛大な処分を求めていたことから、被害額が大きい事案ではあるものの、懲役3年にとどめる判決が下されました。
自社の資金繰りのためにグループ会社で構成する福利厚生組織から3億2,000万円を引き出した
会社経営者が自社の資金繰りのために、ほか2名と共謀し、グループ会社で構成する福利構成組織から3億2,000万円を横領した事案です。
【事案概要】
| ①外国語教室の経営などをおこなう会社の代表取締役Aは、グループ会社で構成する福利厚生組織の会長にも就任していた ②Aは外国語教室の中途解約に伴う返戻金の支払いにより資金繰りに苦しんでいた ③Aは自社社員Bと他社代表取締役Cの2名と共謀したうえで、福利厚生組織から3億2,000万を小切手化し、Cの会社名義口座に入金した |
(大阪地判平成21年8月26日判決)
裁判では、被告人Aが会社の存続のために及んだ犯行であり、反省の態度を示している点は酌むべき事情として扱われました。
しかし、本事案は被害金が高額であるうえ、被害弁償もなされていませんでした。
また、Aが小切手を利用して他社名義の口座に入金するなど、お金の流れをわかりにくくするための巧妙な手口をとっていたことも非難され、懲役3年6月執行猶予なしの実刑判決が下されました。
業務上横領罪の時効
次に、業務上横領罪の時効について解説します。
刑事上の公訴時効と民事上の消滅時効の2つが存在するので、それぞれ詳しくみていきましょう。
公訴時効:横領行為が終了した時点から7年
業務上横領罪の公訴時効は、横領行為が終了した時点から7年で完成します。
公訴時効が完成すると、検察から起訴されなくなるので、その後は刑罰に処されることもありません。
なお、公訴時効は「犯罪行為が終了した時点」から進行するため、被害者が犯罪に気づいたタイミングとは無関係です。
たとえば、横領に誰も気づかないまま7年が経過した場合でも、公訴時効は成立します。
とはいえ、使途不明のお金が放置され続けるとは考えにくいので、公訴時効の成立を期待して罪を逃れようとするのは誤った考え方といえるでしょう。
関連コラム:横領罪の時効は何年?民事・刑事上の時効と時効待ちのリスクを解説
損害賠償請求権の消滅時効:被害者が損害と加害者を知ったときから3年・横領行為から20年
業務上横領罪における損害賠償請求権の消滅時効は、「被害者が損害と加害者を知ったときから3年」または「横領行為から20年」のいずれか早いほうです。
消滅時効が完成すると、被害者から横領の損害賠償請求を受けることはなくなります。
なお、「損害と加害者を知ったとき」とは単なる疑いにとどまらず、損害賠償請求が事実上可能な程度の認識が求められます。
業務上横領が発覚したあとの流れ
業務上横領が発覚したあとの一般的な流れは、以下のとおりです。
業務上横領が発覚すると、まず会社が内部調査をおこない、被害状況を把握します。
被害額や横領期間などが明らかになった段階で、会社側の意向次第では、示談交渉に応じてもらえることもあるかもしれません。
示談が不調に終わった場合は、会社が警察に連絡し、捜査がスタートすることになるでしょう。
捜査中は在宅事件となることもありますが、十分な証拠が集まったうえで逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断されると逮捕される可能性も出てきます。
逮捕された場合は検察に送致され、勾留が決定すると原則10日間・最大20日間にわたって身体拘束を受けなければなりません。
そして、勾留期間中に検察が起訴・不起訴の判断をおこない、起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
業務上横領罪に関してよくある質問
最後に、業務上横領罪に関してよくある質問を紹介します。
業務上横領罪は親告罪?会社が許せば起訴されない?
加害者と被害者の間に親族関係がない限り、業務上横領罪は非親告罪です。
つまり、会社に許してもらえたとしても、警察・検察が捜査を進めて起訴される可能性は残されています。
しかし、実際には会社からの告訴に基づき、捜査が進んでいくパターンが一般的です。
会社が内部調査をおこない、警察に情報を提供してはじめて捜査が本格化します。
関連コラム:業務上横領罪は相対的親告罪!刑が免除されるケースと示談すべき理由
業務上横領の共犯者はどうなる?
業務上横領の共犯に関する刑罰の取り扱いは、以下のとおりです。
| 分類 | 該当するケース | 刑罰 |
|---|---|---|
| 正犯 | 複数人が共謀して横領した場合 | それぞれが「10年以下の懲役」に処される |
| 教唆犯 | 他人をそそのかせて横領させた場合 | 正犯と同等の刑罰に処される(実際には正犯よりも刑罰が軽くなることも多い) |
| 幇助犯 | 横領を手助けした場合 | 正犯よりも減軽された刑罰に処される |
なお、事件に関与した度合いなども量刑に影響するため、裁判ではそれぞれの役割や責任が慎重に判断されることになります。
親族間でも業務上横領は成立する?
業務上横領罪は、親族間でも成立します。
しかし、加害者と被害者が特定の親族関係にある場合は「親族相盗例」に該当し、刑罰が免除されます。
刑罰が免除される親族関係は、配偶者、親・子どもなどの直系血族、同居の親族です。
たとえば、息子が父親の経営する会社で経理を担当し、会社資金を着服した場合、刑罰を受けることはありません。
ただし、犯罪自体は成立するため、民事上の責任が残る点には注意が必要です。
まとめ
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ◆ 業務上横領は「業務上自己が占有する他人の物を不法に自分のものにした」場合に成立する
- ◆ 業務上横領の刑罰は「10年以下の懲役」
- ◆ 業務上横領の量刑には被害金額・犯行の手口・被害弁償の有無などが影響する
- ◆ 業務上横領の公訴時効は7年、損害賠償請求権の消滅時効は3年または20年
- ◆ 親族間の業務上横領は刑罰が免除されることもある
業務上横領罪は、財産犯のなかでも重大な犯罪として位置付けられるものです。
被害金額や被害弁償の有無などによっては、初犯であっても実刑になる可能性は十分あります。
そのため、業務上横領の罪を犯した場合は一刻も早く弁護士に相談してください。
刑事事件が得意な弁護士であれば、個々の状況にあわせて、今やるべきことを的確に提案してくれるはずです。
実際にグラディアトル法律事務所でも、これまで数々の横領事件を取り扱い、解決へと導いてきました。
実践経験豊富な弁護士が24時間・365日体制で対応しているため、少しでも不安に感じることがあれば迷わずご相談ください。
初回相談は無料、LINEでの相談も受け付けているので、お気軽にどうぞ。